|
「かっこよかったよ。香澄くん。さすが、だてにオタクじゃないねえ。初めてでこれだけできれば、スタントでも食っていけるよ」
誉められてるんだか、けなされてるんだかわからない。
青いスクリーンの前で汗を拭きながら香澄は社長の手渡してくれたスポーツドリンクを飲む。
「せめて事前の打ち合わせくらいしてくれればいいのに」
「いやいや、ホントよかったですよ。プロ裸足ですね」
これはスタッフの人だ。
「後でビデオをあげるよ。結構すごい迫力だったね。よくできてるよ、この装置。
これもね、使役品で作ったんだよ。このスタジオでやってることが海の上に再現される。ちょっとCGも入れてるから、ホンキで特撮みたいだった」
そこへ黒羽がスタッフに連れられて入ってきた。
「香澄!」
「やっほう、コウ。どーだった? オレのアクション。役者は無理でもスタントマンにはなれる感じかな?」
なんだかんだ言って、白鳥はすっかりご機嫌だった。
その顔を見て黒羽は、初めてホッとしたように笑った。
「コウも似合ってるじゃん、その服」
黒羽も妙にSFチックな服に着替えさせられていたが、一人だけ上から下まで真っ黒で、少々他の人達とテイストが違う。
「次元刑事ブラック?」
問われて黒羽の顔は赤くなった。といっても、黒羽は先程から進められるままどんどん酒を飲んでいたので、アルコールは既にかなり回っていたのだが。
「そうそう♪ ウルトラマンVS次元刑事ブラック。両者協力して『悪』を倒す。夢の競演じゃないか」
社長はえらく嬉しそうだ。
人の事オタクオタクって言うけど、この社長だってかーなーりー、オタクなんじゃねえの?
しかもウルトラマンで、次元刑事ブラックで、敵がブラックシルバー? オタクの中でもかなりひねてるクチだよな。きらきらピンク、とか出なかっただけマシか。
「おい、マジかよ」
その時いきなり奥の方から声が聞こえた。
「あり? 柳のおっさんの声じゃん。そう言えば見ないと思ったけど」
「おい、葵。これは何かの意趣返しか?」
スタジオの突き当たりにあるドアから、ぶつぶつ呟きながら柳のおっさんが出てきた。
だが、その格好は…。
「ぶっ!」
白鳥は思いっきりスポーツドリンクを吹き出した。
黒羽が慌てて背中をさするが、その黒羽の目も前方に据えられて、大きく開かれている。
「おっさん、それ」
ゲホゲホと思いっきりむせながら、白鳥の顔は、既に笑いで歪んでいた。
柳はたくさんの人がいるのに一瞬ひるんだようだったが、すぐに気を取り直して葵の方を向く。
だが、葵も椅子の上に突っ伏して、懸命に腹を押さえていた。
どう見ても爆笑をこらえているという風情だ。
「…に、似合うぞ柳。最高」
「ばかたれ!」
おっさんは完全にぶーたれていた。
「なんスか? あれ。まだ続きあるんですか?」
白鳥の質問に、葵は体を折りながら、何とか言葉を唇からひねり出した。
「…だ、第2部やろうかなって。悪の幹部の逆襲…」
「だけど、あの格好」
「だって、悪の幹部って言ったら、決まってるだろ?」
そこで白鳥と葵の声が同時に重なった。
『乳のでかい、女幹部!』
言ってから同時に吹き出した。
続いて椅子から転げ落ちるほどの大爆笑。
白鳥も葵も、床を叩いて涙が出るほど笑い転げた。
さすがのスタッフ達も、社長のこれほどの大爆笑は見た事がないらしく、吃驚した顔で突っ立っていたが、やがて彼らも笑いの渦に巻き込まれていった。
そう、柳は女の服を着ていた。
しかも胸元のがばっと開いたヤツである。
ついでに言うなら足はタイツだ。
靴は踵9センチのピンヒール。手には真っ黒な鞭を持っている。
まるきりSMの女王様だった。ただし何かがものすごく間違ってはいたが。
柳のがばっと開いた胸元には、スイカと見間違うばかりの、でっかい丸い乳が揺れていた。
「すげえ、おっさん爆乳じゃん」
「葵、二部はやらないぞ!」
柳が低い声で唸る。
「し、社長、あれ。乳は何で作ったんですか?」
「し、知らない。でもさわり心地はすごくいいぞ。揉んでみるか? 白鳥くん」
「もー、ぜひ。よろしくお願いします」
「黒羽くんにもつけてみるか?」
「そ、それもいいかも…」
2人はもう一度吹き出して、体を折った。
柳は腰に手をあてながら、笑い転げる2人を憮然と見つめた。
別に手などあてたくはないのだが、ピンヒールが不安定で、腰の辺りを支えてないと、なんとなく転びそうな気がするのだ。
しかも造りものの巨大な乳のせいで、腹の辺りがまったく見えない。
だがその立ち方は、偉そうな女幹部そのままだった。
なんか知らんが、楽しそうじゃねえか。
小僧め、葵を怖がってたくせに、肩なんか叩きやがって。
いや、叩いてるのは葵か。
20近くも年が離れてるってのに、まるで学生時代の友達同士みたいに見える。
俺がサカナってーのが気にくわないが、こういう葵が見られるのは、悪くはなかった。
あいつ、友達がいないからな。
女はみんな異性の目でしか葵を見ないし、男も似たようなもんだ。
俺だって、葵の一番近くにはいるけれど、でも、友達じゃない。
あいつが友達を欲しがっている事は知っていた。
だが今となっては、大企業の社長の友達になろうなんて、そんな奴がいるはずもない。
白鳥と友達になった、か…。
まんざら冗談でもなかったんだな。
それなりに本気なのかもしれない。
悪ふざけに肩を叩いて笑いあう友達…。
だとしたら、これはきっと一番欲しいクリスマスプレゼントだろう。
「柳さん…」
気がつくと黒羽がすぐ近くに来ていた。
ピンヒールのせいで2メートルの身長になってしまった柳は、黒羽を見下ろす形になる。
黒羽 高は酔っているのか、白い顔をほんのりと桜色に染めて、妙に色っぽかった。美形は見慣れているくせに、柳は一瞬くらりとする。
いかんいかん。
こいつは普段は威圧的なくせに、時々ビックリするほど男の下半身を刺戟する男だ。
「なんだ?」
「今日は、ありがとうございました。あの、クリスマスプレゼントです」
柳は黒羽から小さな包みを受け取る。
だが、この不安定な格好では、包みは開けそうもなかった。
「ああ。ありがとう。だけど、その…」
「乳の間に入れちゃえ、コウ」
酔ってもいないくせに、白鳥が酔っぱらいのおやじのようなヤジをとばす。
「尻の辺りにポケットがあるぞ、黒羽くん」
葵まで酔っぱらっているのか!?
黒羽はあまり身動きの出来ない柳の尻の辺りを探ると、包みを押し込んだ。
だから! どうして素直にそういう言葉に従うかな、この男は。
黒羽は振り返ると今度は葵に包みを渡した。
「どうぞ、香坂さん」
「ああ、うん」
ほんの少し子供みたいな声で、葵は包みを受け取った。
包みには緑と赤のリボンが簡単にかけてある。
「やあ、砂城の包装だね」
「お菓子です」
黒羽は幸せそうにそう言うと、スタッフの人達にもお菓子の包みを配りはじめた。
柳に続いてドアから出てきた、顔を殆ど仮面で隠した、悪の組織のボスらしい人にも、にっこり笑ってプレゼントを渡す。
全員妙に顔を赤くしてそれを受け取っていた。
「いいね、プレゼントって」
葵は嬉しそうに手の中の包みを見つめた。
「なんかコウの奴、絶対酔っぱらってる。あんなフェロモン振りまいてさぁー」
「嫉妬? そーいえば、白鳥くんだけ貰って無いじゃないか」
「オレには特別なのが、後で絶対あるんですーだ」
「へーえ、特別なのって、どんなのかな? こんなのか?」
言うなり葵は白鳥の頬にキスをした。
「あーっ!」
「ちょっ、ちょっと社長!」
柳と白鳥が同時に叫ぶ。
「いいじゃないか、クリスマスなんだから」
「葵おまえ、酔ってるだろ」
「少しね」
気がつくと葵の手には魔法のようにシャンパンが握られていた。
「みなさん、どうぞ飲んで楽しんでください」
SFチックな銀色のコスチュームのバニーがいつの間にか入ってきて、シャンパンのサービスを始めた。
葵はグラスを高く掲げる。
「メリー・クリスマス!」

スタジオにいた彼らには見えなかったが、いま海上には巨大なクリスマスツリーが投影されていた。
それは夜の海に、きらきらと弾けるように点滅して輝いていた。
「ホント、ゴージャスよねえ」
船の甲板で、柳ひさこがうっとりと海上に浮かぶクリスマスツリーを眺める。
「お嬢さん、一枚」
言われて振り返ると、フラッシュがたかれた。
ひさこは目をぱちくりさせる。
「誰かと思ったら、海里くんじゃない。いたの?」
「もちろん。オレ写真係だから。色々撮らせて貰ってるんです」
「ホント? 怪しい写真とかもある?」
「黒羽さんとか、葵さんとか、ひさこさんの好みのものが、いーっぱいね」
「きゃーっ。絶対焼き増しよ。ぜったいよ」
「もちろん、ひさこさんの頼みとあらば。いいもの厳選してお届けしますよ」
2人は顔を見合わせて、にんまりと笑った。
「あたしねえー、香澄くんと黒羽さんに、着せたいコスチュームあるのよねー」
「その時は絶対写真撮らせてくださいよ」
「わかってるって。取り引き、とりひき♪」
ひさこと海里は共犯者の笑みを浮かべると、腕を組んで歩き出した。

「すみませんね。せっかく用意していただいたんですけど、第2部は中止です」
葵はにこにこと笑いながら、悪の組織のボスに声をかけた。
「なんだ、楽しそうだったのに…」
「それ、気に入られたんでしたら、持ち帰っても結構ですよ」
「そうか?」
ボスはなんとなく嬉しそうだ。
「せめて、記念写真撮りましょうか?」
「その、とんでもない女幹部と一緒にか?」
仮面がぐるりと柳のほうに向けられる。
「私がやりますよ、女幹部」
「…だったら、撮ってくれ」
葵とボスは連れだってスタジオを出ていった。
残された柳は、ふん、と鼻を鳴らす。
「あれ誰? 柳さん。何だか偉そうな感じだけど」
「今日の特別ゲストだよ」
「へえー」
「葵の客。与党の大御所」
「げっ!」
「黙っとけよ」
「誰も信じませんよ、そんな事」
「お前の相棒はどうした?」
「コウなら、何だか酔っぱらってるみたいで。みんなにもプレゼント配るんだって、オレの家族とか、柳さんの家族とか、探しに行きましたよ」
「ずいぶん持ってきたんだな、プレゼント」
柳はあきれたように白鳥を見下ろした。
「大丈夫なのか? 酒強くないんだろう、あいつ。しかもさっきアクションしてたし。相当回ってんじゃないのか?」
「うーん、やばいかな」
白鳥は軽く首を捻ると、黒羽を追って部屋を出ようとした。
だが、ドアの所でくるりと振り返って、にっと笑う。
「柳さん」
「なんだ?」
「それ、すげー似合ってるぞ。今度マジに乳もませて」
「バカ野郎」
柳が腕を振り上げると、白鳥はひひひ、と変な笑いを漏らしながら外へと逃げていった。
「あのガキ」
誰もいなくなった部屋の椅子に、柳はどっかりと腰を下ろす。
せめてピンヒールだけでも脱がない事にはお話にならない。
ヒールに悪戦苦闘していると、尻の辺りが妙にもぞもぞした。
「あ、そうか、黒羽のプレゼント」
手袋を外して尻のポケットを探る。
「菓子だとか言ってたな。潰れてないだろうな」
リボンを外して包みを開くと、中から色とりどりの砂糖菓子が転がり出てきた。
柊の形をしたものや、リースの飾りを象ったものなど、いかにもクリスマスなお菓子だったが、けっして派手なものではなかった。
「砂城の菓子だよ」
声に振り向くと、葵が立っていた。
「なんだよ。お相手はもういいのか?」
「バニー達に一緒に写真撮ってくれって言われて、ご満悦になってる。当分大丈夫だ」
「ああ、そ」
葵は柳の隣に腰を下ろし、そっと胸に手を伸ばす。
「おいおい」
「うーん、やっぱり触り心地がいいなあ。柳今日、それつけたままヤらないか?」
「変態か、お前」
「人の事言えるのか? 俺にメイドの格好させたのはどこの何奴だ」
「あれは、だから、その…。もしかしてこれは、その時の意趣返しか?」
「いや、そんな事今まで忘れてた」
柳はがっくりと頭を落とす。
葵は包みの中から砂糖菓子を摘むと、ひょいと口に入れた。
「おいしい。俺こういう単純な砂糖の味って、好きなんだよな」
「卵焼きも砂糖入りが好きだもんな、お前」
「砂城に帰ってわざわざ買ってきたのかな。まあ下に降りなくたって、スカイでも買えるけど」
「詳しいじゃないか」
「結構好きなんだ、これ。異界浮上大変動の後の砂城で、最初のクリスマスに作られたお菓子だって話だ。災害で物資が不足してたから、単純な砂糖だけで作ったお菓子。平和と愛と、安定への祈願だって。
普通はそれぞれの家で作るんだ。砂城の家庭のお菓子だな。まあ今は店でも売ってるけど。黒羽 高がそんなものを配るなんてね。あの子よっぽど嬉しかったんだな」
「お前も嬉しそうだぞ」
「まあね。気分は悪くない。平和と愛か。陳腐な言葉だが、俺は嫌いじゃないな」
「…変だぞ、葵」
「どこが? 素直だろ?」
「そこが変だ」
「まあ、いいじゃないか、クリスマスなんだし。明日はイブだろ? イブの夜は恋人と一緒にだってさ。あの坊やが言ってたよ」
葵はくすくす笑うと、柳の頬にキスをした。
「だから今夜は、ずっと一緒にいよう」
「お前、酔ってるだろ」
「もちろん。酔っているよ。たまにはいい感じだ。だけどなんだよお前。解ってるぞ。さっきあの子に欲情したろ?」
「う…いや」
「いいさ。あの子はああいう子だ。誰だって欲しくなる。あの子だけ、自分が宝石だって事を知らないんだ」
「おまえだって綺麗だぜ」
「違うよ。そういう意味じゃない。あの子は特別なんだ。本当の意味でのスペシャルさ。だから、今だけでも普通に…」
声はそのまま、小さく口の中で呟かれて消えた。
「鍵のかかる部屋に行こうぜ」
「その格好のままだぞ。でなきゃやだからな」
「バカ」
「バカバカ言うな。俺はそういうのが好きなんだ」
ホストであるにもかかわらず、その後しばらく、2人の姿を見たものは誰もいなかった。


「いやあー、楽しかった。楽しかったー。ごはんも美味しかったし」
パーティーの後、白鳥はすっかりご満悦で、黒羽を、泊まっているホテルまで送った。
楽しかったのか…。
少しぼうっとしながら、黒羽はにこにこ笑う白鳥を見下ろす。
「やっぱ正義の味方はああだよな。敵がブラックシルバーなのが、なんだけどさ。まあショッカーでも一緒か。へっへっへ。一度やってみたかったんだ。役者の才能はないけどなーっ」
白鳥は大きくのびをする。そしてきらきらした目で黒羽を見つめた。
子供みたいだ。
黒羽はなんとなく眩しくて、少し目を細めた。
「見た見た? コウ。オレのウルトラチョップ」
どれがウルトラチョップなんだろう? そうは思ったが、とりあえず頷く。
「何かせわしないけどさ、明日はコウ待望の、家族パーティーだから。でも、今日のも楽しかったよな」
「ああ…」
黒羽は微笑んで頷いた。
知らない人達と、こんなに親しく話した事など無かったと思う。
プレゼントもよく解らないけど、色々配ってしまったような気がする。
誰に配ったのか、もうよく覚えていない。
疲れたけれど、幸せな気分だ。
あの時はみんなが家族のようなつもりになっていた。
たぶん自分はかなり酔っていたのだろう。
今だって、足元も頭も、ふわふわとしている。
「香澄、部屋に来ないか?」
「えええー? 明日の用意しないと」
「少しだけ…」
「うん」
白鳥は陽気に笑うと、黒羽の手を取った。
もちろん少しだけなんて事になる筈はなかった。
白鳥は裸のまま、ホテルの部屋から言い訳の電話を入れる。
「ああ、だからさ、パーティーの手伝いはするって。するってば。いいじゃん、みんな疲れたんだから、もう寝ろよ。オレもコウを送って少し話したら、なんか帰るのかったるくなっちゃって。
…だから、明日コウと一緒に家に行くって。今日はこっちに泊まる。大丈夫、迷惑なんかかけないからさっ」
香澄が頬を少しふくらませて、黙って受話器を黒羽に差し出す。
黒羽は慌ててそれを受け取ると、受話器を耳に当てた。
母親の声が遠い向こうから聞こえてくる。
すいませんね、とかご迷惑を、とかいう言葉に穏やかに頷き、黒羽は受話器を置いた。
「ったく。いいじゃんよ。オレがどこに泊まろーが。いつまでもガキ扱いしやがって」
白鳥が振り向くと、黒羽はうつむいて顔を手で覆っていた。
「えっ? えええ?」
もしかして泣いてる?
オレなんか言った?
白鳥は慌てて黒羽の顔を覗き込んだ。
しかし顔は完全に覆われて、表情はまったく見えなかった。
「なになに? どうしたの」
黒羽の唇から、息が漏れる。
「…母さんの声が、聞こえたような気がした」
「えっ?」
「電話の向こうから。忘れていた。もう母親の声なんて、忘れてた…」
うつむく黒羽の肩が、微かに震えた。
白鳥は目を細めると、その肩を軽く抱き寄せた。
そしてそのまま、ベッドに押し倒して、上に被さる。
黒羽の覆った手を外して、その唇にキスしようとする。
「…みっともない」
黒羽は微かに抵抗して首を振った。
「そんな事無いよ」
なんとか腕を外すと、黒羽はきつく目を瞑っていた。
その顔に白鳥はキスを散らす。
「母さん達さ、すごくコウの事気に入ったみたい。コウ、外は苦手かもしれないけど、でもいつでも来よう。な? オレと一緒に、また来よう」
「香澄…」
黒羽はやっと瞳を開ける。白鳥の微笑む顔がすぐ近くにあった。
「でも、今晩はオレと、こうしていようなっ」
くすくすと笑う。
「やっぱさ、家族パーティーもいいかもしんないけど、クリスマスは恋人とだぜ。ホント言うと、オレ初めてなんだ。そういうの。だから、なっ。イブになる夜は、コウと。こうやって、キスして、抱き合って。それで…」
いきなり白鳥は言葉を切り、目を丸くした。
「あっ…」
「なに? 香澄」
白鳥の声に、黒羽も少し顔を上げる。
「コウ、外…」
指さす窓の向こうには、ぼんやりと白いものが見えた。
「雪だ…」
少しだけカーテンを開けて、黒羽と白鳥は隙間から外を覗いた。
顔を上に向けると、都会の明るい空からふわふわの牡丹雪が舞い降りてくる。
「寒いはずだね。ホワイトクリスマスだよ」
ガラスに顔を押しつけて雪を見ていると、アッという間にガラスが息で白く曇ってしまった。
「コウ」
曇った窓を透かすように、それでも珍しそうに雪を見上げる黒羽の体を抱きしめる。
黒羽も視線を窓から戻して、白鳥の体に腕を廻した。
体は暖かかった。
そのままベッドの中に倒れ込む。
「コウ。明日、パーティーが終わったら、うちへ帰ろう」
「香澄…」
敏感な所を触られて、黒羽の体がぴくりと動く。
「オレと2人で砂城に帰ろう。オレ、一週間もコウと会ってなくて、すごく寂しかったよ。コウは?」
「うん、香澄…。僕も、会いたかった」
「会って、こうしたかった?」
黒羽は黙って頷く。
「寂しくて、なんとなく不安だった。僕は、情けない…」
「少しくらい、情けなくしててよ。でないとオレ、立つ瀬無いからさ」
白鳥は黒羽の白い体をうっとりと眺める。
うん、やっぱオレ、こうしていたい。
オレの帰る所は、いつの間にか砂城になってる。
あそこが、今はオレの家だ。
砂城はコウのいる場所だから。だから、一緒に砂城に帰ろう。
一緒に家へ帰ろう。
時々もしも、煩い家族の一員になりたくなったら、オレと一緒にまたこっちへ出てくればいい。
二人っきりもいいけど、たまには鬱陶しくなるまで大勢に囲まれてみるのもいい。
ねえコウ。
そんな風に暮らしていこう。
「香澄」
「なに?」
「香澄へプレゼントを渡していない」
おっ、一応気付いていたのか。
といっても、そういえばオレだって無いんだよな、プレゼント。
考えてなかったぜ。
「いいよ、オレもコウにあげるプレゼント無いし」
それに、コウといい事しちゃって。
これって、プレゼントはあたしよ、みたいな感じじゃん。
うーん、どうせこうなるなら、リボンでも体に巻いて貰って、そのセリフ言って欲しかったかも。
むむむ。悪くない。もしかしてオレって、結構シチュエーションフェチ?
「でも、何かあげたい」
うへー。可愛いセリフ。じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。
「そうだなー、それじゃあ」
白鳥は黒羽の耳元で何かを囁いた。
黒羽の顔があっと言う間に赤く染まっていく。
「プレゼントしてくれるんだろ?」
嬉しそうに言う白鳥の下で、黒羽は唇を結んで、少しだけためらった後、やっと白鳥をまっすぐに見つめた。
そして口を開いた。
「香澄。愛してる…」
「やったあー。コウ」
白鳥は叫ぶと、黒羽の体を抱きしめた。
「もう一度、コウ」
「一度でいいって…」
「そんな事言ってない。プレゼントしてよ」
黒羽は困ったように眉をひそめたが、太陽のように笑う白鳥に、逆らう事は出来そうになかった。
「…愛してる」
「うん、もう一回」
「愛してる、香澄」
「うん、うん」
「香澄…愛してる…」
心を言葉にするのは苦手だった。
でも、香澄が望むのなら、何度でも言おう。
僕はきっと酔っている。
何に? 酒に? 香澄とこうして抱き合っている事に?
自分は幸せに酔っているのだ、という事を、黒羽はついに気付かなかった。
ただ心も体も、ふわふわと暖かかった。
12時の鐘がどこか遠くからかすかに聞こえる。
街はクリスマス仕様になっていて、鐘の音も聖夜にふさわしい響きだ。
メリー・クリスマス…。
2人は雪の向こうから聞こえてくる鐘の音に耳を澄ませながら、そのまま朝まで抱き合って眠った。

次の日は家族パーティーだった。
「普通のパーティーだぜ。七面鳥に詰め物なんかしないよ。ケンタッキーでパーティーセット買ってくるんだ。ケーキは趣味でお袋が焼くけどな」
そう言った白鳥は、テーブルの上に様々な料理が並んでいるのを見て、目を瞠った。
「七面鳥、じゃないけど、詰め物チキンじゃん」
「香澄くん、まだ手を出さない!」
兄貴の嫁さん、加夜子ちゃんが腰に手をあてて軽く睨む。
「あっ、これ、加夜子さんが作ったの?」
「ふっふっふ。憧れだったのよ、これ作るの。これのためだけに料理教室に通ったんだから」
自慢になるんだか、ならないんだか。
加夜子さんはVサインを出す。
パーティーはにぎやかに始まった。
なにせ総勢9人が狭い部屋にぎゅう詰めになっているのだから、賑やかにならざるをえない。
ちょっと待て、9人?
「どうしてお前がいるんだよ、海里」
「香澄、お友達に乱暴な口をきいちゃいけません」
「友達かよ、こいつが」
「ちゃんと今日は招待していただいたんだよ。オレはここにいる権利があるの」
言いながら海里はローストビーフに手を出す。
「どうして? どうしてこいつを招待?」
膨れる香澄に、母親は嬉しそうに答える。
「だって、昨日は香坂さんに招待して貰ったわけだし。香坂さんは今日はお仕事で忙しいそうだし」
「だからオレが代理♪ 昨日ご挨拶したんですよねー」
海里と母親は、ねー、と楽しそうに顔を見合わせた。
この野郎。不良のくせにオバサン受けのいいヤツめ。
「代理って、母さんこいつ、香坂さんの親戚でもなんでもないぜ」
「でも代理でいいって、香坂さんが言ってらしたわよ」
そりゃあ、代理になったっていいんだろうけどさ。
何せこいつはあの、篁一族だ。
…母さん、こいつの正体知ったら、そんな呑気な顔してられないぜ。
香坂は単なる企業の社長だけど、篁は…華族の流れだからな。
だけどもちろんそれは言わない。
いくら憎たらしくても、他人が本気で言って欲しくないことをばらす趣味はオレにはない。
海里だって、オレ達のことは家族には言わないでくれてるもんな。
「だけど海里、お前今日は、お前の所のパーティーじゃなかったのかよ。そう言ってたろ?」
「んー? そんな事言ったか? オレのパーティーは昨日だけど?」
「昨日って、ありゃお前のパーティーかよ、違うだろっ」
「オレが、参加するパーティー。だよ」
なに言ってやがる。お調子野郎め。
だいたいにおいて、お前のパーティーはささやかだった筈だろっ?
あの豪華客船のパーティーのどこがささやかなんだよ!
それともささやかってーのは、金持ちの嫌味かっ。
心の中で悪態をついているうちに、海里はさっさと黒羽の近くに腰を下ろした。
ああっ、てめー。すばやいヤツ。
「ほらほら、黒羽さん。昨日の写真も持ってきたんだよ」
わあー、とか、きゃあー、とか言いながら女性陣がパーティーの写真を見つめる。
「お母さんも綺麗に撮れてますよ。おねーさんも、ほら」
「あらホント。結構いいじゃない。焼き増ししてくださいね、海里さん」
「もちろん。今日の写真も撮りましょうか? オレプロですから、美しい人達は、より美しく撮りますよ」
海里のヤツは、すっかり家族の中に溶け込んでしまった。
むー。そういう人当たりのいい所は、天性のモノなのか?
女受けもえらくいい。
もしかして女の兄弟がいたりするのかもしれない。
実を言うと、男ばっか3人もで、乱暴にがさつに育つと、女の子とどう話していいのか解らなくなったりする事があるんだよな。
その証拠に兄貴2人は女性陣に置き去りになっている。
(聡兄なんか、新婚なのにだ)
コウは、というと、コウはまた別格だった。
なにせテレビで見る美人女優なんか、遙か遠くに置き去りにするくらい綺麗な男なのだ。
自分たちの命の恩人だと覚えていなかった兄貴達も、時々眩しそうにコウの顔に見とれている。
そんな男を、綺麗なものが大好きな女達が、放っておく筈もない。
最初から周りを囲んで、きゃあきゃあ騒いでいる。
コウは口べたで海里みたいに会話で盛り上げる訳じゃないんだけど、どうやらコウみたいな綺麗な男は、真ん中で座っているだけでもいいらしかった。
こんな風に女を全部独り占めしちゃうような男なんて、本来なら嫉妬と羨望の対象になってもいいんだけど。
でもこれだけレベルが違って綺麗だと、張り合う気持ちもなくなるらしい。
兄貴達も別にどうという事無く、いつもより豪華なクリスマスディナーを、せっせと腹に詰め込んでいた。
いやむしろ、どちらかというと、コウを女の子達に混じった綺麗なものの一つとして見ている感じがする。
うーん、どうなんだ、それって。
ホント言うと、男にそんな風にコウが見られるのは、オレとしては気が気じゃない。
ああ、惚れちゃったんだから仕方ないけど、でもオレって、とっても大変な道を選んじゃったよな。
なんか少しだけ、そう思うよ。
しかし母親でさえ、顔を赤らめてコウの顔に見とれていた。
女ってヤツは何歳つになっても、たとえ母親でも変わらないものなのかもしれない。
「香澄をよろしくお願いしますね」
そう言って見上げる母親の顔を、とっても嬉しそうにコウも見返して、熱心に頷いていた。
まあ、母さんの言っているのは、なにせオレの命の恩人な訳だし、危ない砂城にいても、コウと一緒なら悪くないんじゃないか、って事なんだろうけど。
だけどオレ達の関係を考えると、まるでオレがコウに嫁に貰われていくようなセリフに聞こえるぜ。
むー。一応オレがタチなんだから、逆と言えば逆だ…。
もちろんそんな事ここで言えっこないけどな。
まあそのうちな。そのうちゆっくり。
オレはワインを自分のグラスにガバガバ注ぎながら、微笑むコウの顔を見つめた。
言わなくても、もしかしたら自然にバレちゃうかもしれないけど。
オレ達まだまだ途中だし。
愛してるって言葉も、プレゼントとして、やっと言ってもらった感じだし。
もうちょっと2人で歩いたら、もっと穏やかに自然になれたら、そうしたら、そのうちきっと…。
だから今は、あと少しだけ秘密の恋人でいよう。
2人だけの秘密も、わくわくする。
きっと楽しいよ、コウ。
(ここにいる海里が先刻ご承知な事は、この際無視する事にした)
「昨日のビデオもあるんですよ、みんなで見ましょう」
海里が昨日の特撮ショウを撮ったビデオを陽気に振り回すと、全員がテレビの前に集合した。
おっ、オレがやったヤツか。
それはちょっと見たいかも。
テレビのほうに行こうとしたオレの目に、海里が持ってきた写真の束が映った。
…あっ。
どきりとする。
コウの笑った顔。
その写真に写ったコウの顔は、驚くほど綺麗だった。
酒に酔っているのか、ほんのりと桜色の肌。
メガネを外した表情からは、いつも纏っている硬質なイメージも無くなっている。
柔らかいソフトフォーカスの光。
コットンキャンディーのような、ふわりとした写真。
たぶん酒を飲まされて、誰かと話している一瞬を捉えたのだろう。
朝露の中で花が開くような、それは、その瞬間だけで消えてしまう美しさだった。
またたきしたら、きっと見逃してしまう。
そんな儚い時間を切り取った写真。
「…欲しいだろ、それ」
後ろから海里が肩越しに覗き込む。
「わっ。いきなり背中に立つなよっ」
「オレのプライベート写真集のトップにする予定だ」
「ううう…」
「こっちには、次元刑事ブラックの黒羽さんもいる。超カッコいいぞ」
海里は写真をひらひらさせた。
くそーっ。それがオレの憧れのヒーローだって知っての狼藉かっ。
「ううっ」
「欲しいか。欲しいって言えよ」
「…欲しい」
「一枚300万円だ」
「オヤジか、てめえ」
海里はげらげら笑いながらカメラを構えた。
今日の家族パーティーの写真は、その後オレ達のアルバムの1ページを鮮やかに飾った。
怒ってるオレとか、女の子達に囲まれてシャンパンを飲むコウとか、銀紙を貼った紙の三角帽をかぶせられた兄貴と嫁さんとか。
それは本当にささやかな家族のパーティーだった。
そしてアルバムの中には、あのコウの写真も貼られたのだった。
300万円は、もちろんしなかった。


「海里…」
目の前の写真の束を見ながら、葵は頭を抱えていた。
海里は応接室のふかふかのソファーに座りながら、にやにやと笑う。
「こんなものまで撮ったのか、お前」
指さす写真には、巨乳女幹部に扮した葵と、その腰に手を回している悪の組織のボスの姿が写っていた。
「他にもあるよ、葵さん。女幹部の柳さんとか」
「柳は良いよ、別に。だけどこれは…」
「総理だろ? 知ってるよ。シークレットなゲストだ。うん。だけどこれ、プライベートな写真だもん。現像だってオレがしてるしさ。流失はさせないよ。葵さんの分だけ、持ってきたんだ。それに仮面で顔隠してるじゃないか。全然誰だか解らないって」
「それはそうだが…」
黒羽が嬉しそうにボスにお菓子を渡しているシーンも写っている。
いったいどうやって撮ったんだ?
スタッフの中にこっそり紛れていたとしか思えない。
「そのうちみんなに、プライベートな写真集を作って送ったげるよ」
「ヤバイのだけは抜いといてくれ」
「オッケー。その辺はまかしといて。ヤバイのは全部オレの完全な個人所有にするつもりだからさ」
へへへ、と海里は笑う。
葵も苦笑した。
どうもこの子供には気を許してしまう所がある。
「柳の女幹部は、広報に載せよう」
「ええっ、マジ? 怒られない?」
「最近あいつは妙に偉そうに気取ってやがるからな。たまには女の子にきゃあって笑われるのもやっておくべきだ」
「なーんか、言い訳くさいなあ…」
ぶつくさ呟く海里に、葵はニヤリと笑った。
「それより海里。今度はこれを届けてくれ」
渡されたそれに、海里は目を丸くする。
「作ったんですか? それ」
「特注♪」
「これはいくらなんでも、買わせられないですよ」
「大丈夫。だって白鳥くんの注文なんだから。向こうは忘れているかもしれないけど、こっちは忘れない。代金はそのうち体で、って言っといてくれ」
「こえ〜」
海里と葵は顔を見合わせて、にっこりと笑った。

数日後、警察の寮にとんでもないシロモノが届いた。
「そりゃ、いいかもって言ったけどさあ…」
黒羽は呆然と口を開け、白鳥は頭を抱える。
箱の中からでてきたのは、黒のラバーで作った女幹部の衣装だった。
黒羽の体にジャストサイズ。
もちろん巨大な乳もついている。
「あの社長、絶対嫌がらせだってば」
「香澄、これ…」
「どーする? 新年会か、来年の忘年会で余興に使う?」
そんなん見たら、絶対みんなひっくり返る。
いっそのこと、ベッドで使っちゃうってーのも、手かもしれないけど。
女幹部の衣装と一緒に、パーティーで着たウルトラ警備隊の服やら、次元刑事ブラックの服やら、ウルトラマンの着ぐるみまで入っている。
こんなんベッドで着たら、CG使うようなエッチしなきゃならねえよな。
しょーもないことを考えながら、白鳥はため息をついた。
しかし…。
どうしてあの社長はコウのサイズを知ってるんだろう?
白鳥は首を捻る。
だがそれだけは、永遠の謎なのだった。
END

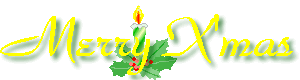

|